
小説作品をこわし、はみ出してしまうのだ
坂口安吾は昭和初期(アテネ・フランセの友人らと制作した同人誌「言葉」にマリイ・シェイケビッチ原作「メランジェ――プルウストに就てのクロッキー」の翻訳を載せたのが昭和5年、翌6年に「木枯の酒倉から」を同誌に発表)から、昭和中期(「世に出るまで」を小説新潮に発表したのが昭和30年、同年没)にかけて活躍した小説家。
東洋大学印度哲学学科卒業であることが知られているが、前述した外国語学校アテネ・フランセにも通学している。ちなみにこのアテネ・フランセは東京都千代田区神田にまだある。
学生時代から一風変わった性格の持ち主(正確に言えば幼少期からだろうか)で、大学入学以来悟りを開こうとして、1日睡眠4時間の生活を1年半送ったそうだ(そのころ二十一であった。睡眠は一日に四時間ときめ、十時にねて、午前二時には必ず起きて、ねむたい時は井戸端で水をかぶった。――小説「二十一」より引用)。
これが因で神経衰弱にかかったというから、凄いのか何なのだか常人には判断がつかない。なお、この神経衰弱は梵語、パーリ語、チベット語、フランス語、ラテン語などを学ぶことで克服した(十時間辞書をひいても健康人の一時間ぐらいしか能率はあがらぬけれども、二六時中、目の覚めている限り徹頭徹尾辞書をひくに限る。梵語、パーリ語、チベット語、フランス語、ラテン語、之だけ一緒に習った。おかげで病気は退治したが、習った言葉はみんな忘れた。――小説「二十一」より引用)。
こうした逸話に事欠かない氏だが、かかる生命力は小説にも存分に息づいている。その勘所をうまく捉え、言語化に成功したのが文芸評論家の奥野健男氏だ。
「――坂口安吾の書くものには、文壇巨匠とか文豪とか、小説の名人とかいわれる文学者たちの、すぐれた作品にも、もとめることができない不思議な人間的魅力にあふれているのだ。ある時は人間の魂の底まで揺るがすようなすさまじい感動を、ある時は澄みきった切ないかなしみに似た憧れを与えてくれるが、多くの場合、小説作品の構成をのり超え、小説作品をこわし、はみ出してしまうのだ」
坂口安吾が書く文には、並々ならない生きる力や物事を見通す目があるがための悲しさが宿っているように感じる。こうした言葉の数々に励まされることがある。なぜ好きなことをして暮らしていけないのだろう、そもそも好きなこととはなんだろう、好きなことをしているけれど裕福な暮らしにならない、そもそもお金はそんなに大事なものなんだろうか、漠然と生きづらさを感じている、社会に認めてもらえない、自分の考えはおかしいのだろうか。そんな悩みや煩わしさを解決してくれるヒントになるのではないかと思う。少しだけだが、そんな坂口安吾の名言や名文を紹介したい。
現代に生きる人にこそ読んでほしい、坂口安吾の名言・名文
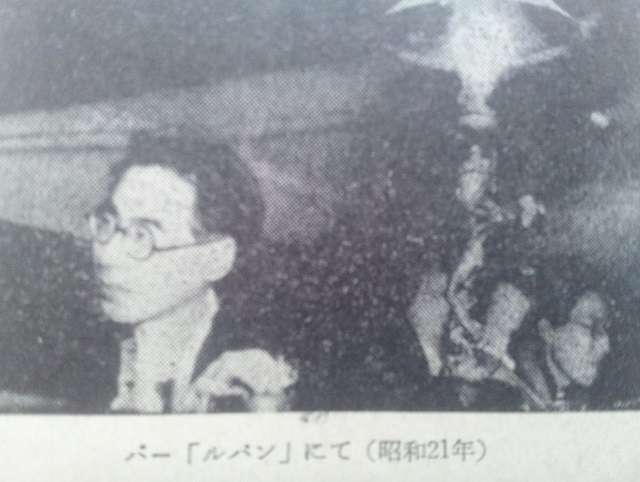
思想と文学の果実を最後の成熟のはてにもぎとろうと思っている
「私は最大の豪奢快楽を欲し見つめて生きており多少の豪奢快楽でごまかすこと妥協することを好まないので、そして、そうすることによって私の思想と文学の果実を最後の成熟のはてにもぎとろうと思っているので、私は貧乏はさのみ苦にしていない」――「いずこへ」
何か一つの純潔と貞節の念が大切なものだ
人間の生き方には何か一つの純潔と貞節の念が大切なものだ。とりわけ私のようにぐうたらな落伍者の悲しさが影身にまで沁みつくようになってしまうと、何か一つの純潔とその貞節を守らずには生きていられなくなるものだ。――「いずこへ」
一番汚いところまで、行けるところまで行ってやれ。そして最後にどうなるか、それはもう、俺は知らない
そして、私に泊らないかと言う時には、いつもギラギラした眼で笑っていた。 私は今度こそあのスタンドへ泊ろうと思った。一番汚いところまで、行けるところまで行ってやれ。そして最後にどうなるか、それはもう、俺は知らない。――「いずこへ」
正義! 正義! 私の魂には正義がなかった。
私の女の魂がともかく低俗なものであるのを私は常に砂を噛む思いのように、噛みつづけ、然し、私自身がそれ以上の何者でも有り得ぬ悲しさを更に虚しく噛みつづけねばならなかった。正義! 正義! 私の魂には正義がなかった。正義とは何だ! 私にも分らん。――「いずこへ」
孤独が悟りの第一条件だと考えていた
当時僕には友達がなかった。たくさん有ったが、僕の方から足を遠くしたのである。なぜなら、僕が坊主になろうというのは、要するに、一切をすてる、という意味で、そこから何かを掴みたい考えであり、孤独が悟りの第一条件だと考えていた。――「二十一」
食わなくとも酒はのむというような生活であった
私はまったくの無能力者であった。私の小説などは一年にいくつと金にならず、概ね零細な稿料であり、定収にちかいものといえば、都新聞の匿名批評ぐらいのもの。それとて二十円ぐらいのもので、あとは出版社や友人からの借金で、食わなくとも酒はのむというような生活であった。――「三十歳」
オレは天才だから不遇で貧乏で怠け者なんだ。そうあの人に言わせようとしていたのだ。
ありていに云えば、正体はむしろこうであったろう。あの人の本心が私のことをあなたは天才だからと云っているのではなく、私の虚栄深い企みの心が、オレは天才だから不遇で貧乏で怠け者なんだ。そうあの人に言わせようとしていたのだ。あの人はその私の虚栄のカラクリの不潔さに堪えがたいものがあったのだ。――「三十歳」
あなたこそ、小さな虚しい盛名に縋りついているんじゃないか。その盛名が生きがいなんだ。虚栄なんだ。見栄なんだ。
私は冷たく考えた。事実、私は卑屈そのものであった。彼女の心は語っている。私の貧困と、私の無能力がみずぼらしくて不潔だと。よろしい。私は卑屈に、うけいれる。じっさい、私は不潔で、みすぼらしい魂の人間なんだ。然し、そういうあなたの本心はどうだ。あなたこそ、小さな虚しい盛名に縋りついているんじゃないか。その盛名が生きがいなんだ。虚栄なんだ。見栄なんだ。その虚栄が、恋心にも拘らず、私の現実を承認できないのじゃないか。――「三十歳」
私はつまり思いあがっていたのだ
私はそれだけの人間でもあるのだ。なぜそれだけの人間として、矢田津世子の凡庸な虚栄につつましく対処し、うけいれることが出来なかったのだろう。私はつまり思いあがっていたのだ。――「三十歳」
非常である。ただ激しい。
そうしてただ同じ海辺を行ったり戻ったりしていたのである。生命を賭した一念が虚しく挫折したとき、この激しさが当然だと思わずにいられない。これが仕事に生命を打ち込んだときの姿なのである。非常である。ただ激しい。落胆とか悲しさを、その本来の表情で表現できるほど呑気なものは微塵もない。畳の上の甘さはこういう際にはあり得ないのだ。――「真珠」
弱者の道はわかりきっている
私は弱者よりも、強者を選ぶ。積極的な生き方を選ぶ。この道が実際は苦難の道なのである。なぜなら、弱者の道はわかりきっている。暗いけれども、無難で、精神の大きな格闘が不要なのだ。――「恋愛論」
この現実を一つの試練と見ることが俺の生き方に必要なだけだ
ままよ、伊沢の心には奇妙な勇気が湧いてきた。その実体は生活上の感情喪失に対する好奇心と刺戟との魅力に惹かれただけのものであったが、どうにでもなるがいい。ともかくこの現実を一つの試練と見ることが俺の生き方に必要なだけだ――「白痴」
爆発の足が近づく時の絶望的な恐怖
爆弾という奴は落下音こそ小さく低いがザアという雨降りの音のようなただ一本の棒をひき、此奴が最後に地軸もろとも引き裂くような爆発音を起こすのだから、ただ一本の棒にこもった充実した凄みといったら論外で、ズドズドズドと爆発の足が近づく時の絶望的な恐怖ときては額面通りに生きた心持がないのである。――「白痴」
絶望が発狂寸前の冷たさで生きて光っているだけだ
ザアと雨降りの棒一本の落下音がのびてくる。爆発を待つまの恐怖、全く此奴は言葉も呼吸も思念もとまる。いよいよ今度はお陀仏だという絶望が発狂寸前の冷たさで生きて光っているだけだ。――「白痴」
彼は見た。白痴の顔を
押し入れの中で、伊沢の目だけが光っていた。彼は見た。白痴の顔を。虚空をつかむ絶望の苦悶を。――「白痴」
僕はね、仕事があるのだ
僕はね、ともかく、もうちょっと、残りますよ。僕はね、仕事があるのだ。僕はね、ともかく芸人だから、命のとことんのところで自分の姿を見凝め得るような機会には、そのとことんのところで最後の取引をしてみることを要求されているのだ。――「白痴」
この素朴な切なさを一生の心棒にして生を終るのであろうと思っている。
尤も私は六ツの年にもう幼稚園をサボって遊んでいて道が分からなくなり道を当てどなくさまよっていたことがあった。六ツの年の悲しみも矢張り同じであったと思う。こういう悲しみや切なさは生れた時から死ぬときまで発育することのない不変のもので、私のようなヒネクレ者は、この素朴な切なさを一生の心棒にして生を終るのであろうと思っている。だから私は今でも子供にはすぐ好かれるのはこの切なさで子供とすぐ結びついてしまうからで、これは愚かなことであり、凡そ大人げない阿呆なことに相違ないが、悔いるわけにも行かないのである。――「石の思い」
古い思い出の匂がした
白い燈台があった。三角のシャッポを被っていた。ピカピカの海へ白日の夢を流していた。古い思い出の匂がした。――「ふるさとに寄する讃歌 夢の総量は空気であった」
何か求めるものはないか?
長い間私はいろいろのものを求めた。何一つ手に握ることができなかった。そして何物も摑まぬうちに、もはや求めるものがなくなっていた。私は悲しかった。しかし、悲しみを摑むためにも、また私は失敗した。悲しみにも、また実感が乏しかった。私は漠然と拡がりゆく空しさのみを感じつづけた。涯もない空しさの中に赤い太陽が登り、それが落ちて夜を運んだ。そういう日が毎日続いた。
何か求めるものはないか? ――「ふるさとに寄する讃歌 夢の総量は空気であった」
人間の親密さを受けとめるに足る弾力は、私の中に已になかった
姉は聡明な人であった。子供のために、よき母であった。そのために、姉は年老いて、少女の叡智を失わなかった。姉は私を信じていた。それ故、私は姉に会うことを欲していなかった。全て親密さは風景である私にふさわしくなかった。それは、苦い刺激を私に残した。私は襤褸であった。人の親密さを受けとめるに足る弾力は、私の中に已になかった。――「ふるさとに寄する讃歌 夢の総量は空気であった」
私は目を閉じて、知らぬ顔をした
同じ土地に姉の病むをききながら見舞に行くことを、毎日見合わせた。彷徨の行きずりに、ときどき、薬品の香が鼻にまつわった。私は目を閉じて、知らぬ顔をした。私はアイスクリームを食べた。匙を、ながく、しゃぶっていた――「ふるさとに寄する讃歌 夢の総量は空気であった」
よろしい、ダンスを習おう
私は汽車の中で考えつづけた。だいたいダンスホールへ這入っていながら踊らないなんてことがこういう阿呆な感傷に落込むもとなんだ。ダンスホールのソファに埋もれ、踊りもしないでボンヤリしているなんてことは、まったく古典的な精神的風景美があるからな。この風景美は大いに排撃すべきだ。よろしい、ダンスを習おう。――「流浪の追憶」
希望に燃え、虚名にあこがれ、成功を追いながら、死の正しい意味を知る者はただ青春のみ
少年の希望のなんと暗くあることよ。貧乏の苦も、恋の苦も知らず、多くの汚れを知らず、ただ人生の重さだけを嗅ぎ当てている。希望に燃え、虚名にあこがれ、成功を追いながら、死の正しい意味を知る者はただ青春のみ。最も希望のない時期だ。そういうことも言えると思う。――「青い絨毯」
要するに仇心、遊びと浮気の目であった
若い目と目が人並みを距ててニッコリ秘密に笑いあうとき、そこには仇な夢もこもり、花の匂いもまた流れ、若さのおのずからの妖しさもあったが、だからまた、そこには退屈、むなしさ、みずから己れを裏切る理知もあった。要するに仇心、遊びと浮気の目であった。――「青鬼の褌を洗う女」
相撲という勝負の仕組みはまるで人間を侮蔑するように残酷なものに思われた
相撲の勝負はシマッタと御当人が思った時にはもうダメなので、勝負はそれまで、もうとりかえしがつかない。ほかの事なら、一度や二度シマッタと思ってもそれから心をとり直して立ち直ってやり直せるのに、それのきかない相撲という勝負の仕組みはまるで人間を侮蔑するように残酷なものに思われた。――「青鬼の褌を洗う女」
余程の悪徳と考えたらしく
数日後少女から手紙がきた。兄が無事帰ったという知らせで、自殺する筈の男が海水浴に行っていたということをを余程の悪徳と考えたらしく兄に代わって弁解と詫びが連ねてあった。――「篠笹の陰の顔」
発狂といっても日常の理性がなくなるだけで、突きつめた生き方の世界は続いている
発狂といっても日常の理性がなくなるだけで、突きつめた生き方の世界は続いている。むしろ鋭くそれのみ冴えているのである。――「篠笹の陰の顔」
私には、これらの婦人と現実の婦人たちとの関聯か類似がはっきりとしない
内藤ジュリヤ、京極マリヤ。細川ガラシャ。ジュリヤおたあ。死をもって迫られて向主を棄てなかった。婦人達、私の安易な婦人感とはたいぶんに違った人達であった。私には、これらの婦人と現実の婦人たちとの関聯か類似がはっきりとしない。どういう顔をしていただろうか。日常の弛んだ心にも主の外に棲むことはできなかったのだろうか。そして肉体の中にも?――私には分からないのである。この現実とつなぎ合わせる手がかりが見当たらないのである。――「篠笹の陰の顔」
人の命令に服すことのできない生まれつき
人の命令に服すことのできない生まれつきの私は、自分に命令してそれに服するよろこびが強いのかもしれない――「風と光と二十の私と」
ほんとうに可愛い子どもは悪い子どもの中にいる
ほんとうに可愛い子どもは悪い子どもの中にいる。子どもはみんな可愛いものだがほんとうの美しい魂は悪い子どもがもっているので、あたたかい思いや郷愁をもっている。――「風と光と二十の私と」
要は魂の問題だ。落第させるなどとは論外である
年はほかの子どもより一つ多い。腕っぷしが強くほかの子どもをいじめるというので、着任のとき分教場主任から特にその子どものことを注意されたが、実は非常にいい子どもだ。(中略)遊びに行ったら躍りあがるように喜んで出てきて、時々人をいじめることもあったが、ドブ掃除だの物の運搬だの力仕事というと自分で引き受けて、黙々と一人でやりとげてしまう。先生、オレは字は書けないから叱らないでよ。その代わり、力仕事はなんでもするからね、と可愛いことを言って私にたのんだ。こんな可愛い子がどうして札つきだと言われるのだが、第一、字が書けないということはとがむべきことではない。要は魂の問題だ。落第させるなどとは論外である。――「風と光と二十の私と」
自分の野心が悲しいと思っていた
私はしかし先生で終わることのできない自分の野心が悲しいと思っていた。なぜ、身を捧げることができないのだろう。――「風と光と二十の私と」
君、不幸にならなければいけないぜ
彼らいつも私に、こう話しかける。君、不幸にならなければいけないぜ。うんと不幸にね。そして、苦しむのだ。不幸と苦しみが人間のふるさとなのだから、と。――「風と光と二十の私と」
まとめ
一部を切り取ると前後のつながりがわからないので、どういう意味なのだか十分に理解できないかもしれない。そんなときはぜひ、その作品を読んでみてほしい。自分のための名言が見つかるはずだ。



コメント